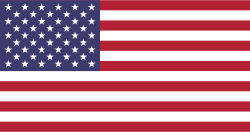公開している記事の「無断引用」、「無断転載」は禁止しております。
ここで公開している話はすべてオリジナル小説で登場する人物、場所は架空でありフィクションです。
体調が悪い時は逆に健康に悪化させる可能性があるため読むのを中止にしてください。
まだ昭和だった時代、僕の生まれ育った田舎町の西側に、双子山という山があり、そこにはアズナ村という集落があると噂されていた。
双子山の由来は同じ高さの山頂があるからだとわかったが、アズナ村の方は漢字も名前の由来もわからなかった。
双子山のどこかに鈴のついた杖が二本地面に刺さっていて、その間を通ると村に入ることができる。しかしむやみに立ち入ってはならない。
もしもアズナ村に入って一度でも息を吸ったら、アズナ村から出られなくなる、と言い伝えられていた。
幼い頃の僕はその言い伝えに素直に怯えて双子山には立ち入らないようにしていたが、同級生たちの中には虫取りや魚釣りのために度々山に入る者がいた。
時には大人たちが血相を変えて山に入った子どもを捕まえることもあった。
そんな大人たちを面白がって、やんちゃな子どもがまた双子山に入る。そんないたちごっこを繰り返していた。
ある夏の日、僕の弟の友達が双子山で行方不明になった。
ちょうど夏休みの時期だったが、僕たち子どもは双子山への立ち入りを禁じられ、大人たちは一か月近くいなくなった子を探していた。
夏休み明けの始業式の日に、弟の友達の机は教室から撤去された。
弟が大人たちに友達のことを尋ねても、皆そんな名前を知らないかのように首を傾げたという。
弟の同級生は気味悪がって、大人たちと同じようにいなくなった子のことを最初からいなかったものとして扱った。
仲の良かった弟だけは、どうしても友達を見捨てられず、一人で双子山を散策し続けた。
両親は弟を叱ったが、弟は止まらなかった。
しかたなく僕が弟を見張ることになった。
何かあったら僕が弟を危険から守ること、そう両親に約束させられた。
弟は双子山をくまなく捜索した。
山のふもと、山頂、奥にある崖や流れの急な川にも足を踏み入れた。
秋が深くなにつれ双子山は赤く色づき、やがて落ち葉も増えて枯れ枝が目立つようになった。
吐息が白くなる頃、双子山唯一の滝の前で、僕は弟に「もうあきらめた方が良い」と言った。
弟は涙目になって項垂れた。僕は弟が納得したものだと思った。
だがその夜、寝静まった家の玄関が開く音が微かに聞こえて、僕は布団から跳び起きた。
弟の布団には誰もいなかった。
僕は出ていったであろう弟の後を追いかけて夜の双子山へと分け入った。
親を呼べばよかったと今なら思うが、そのときは弟を守ると言う約束を守ることに執着してしまっていた。
暗い山の道では月と星の明かりだけが頼りだった。
もちろんそれでは足らず、石や雑草に幾度も足を取られた。
どうにか滝のところまで行って弟の名前を叫んだが、木々の風に揺れるばかりで、弟の返事はなかった。
滝つぼに映る月を見て、僕は視界を滲ませた。
弟の名前を呼ぼうにも嗚咽が先にきて言葉にならなかった。
項垂れた僕の耳に、鈴の音が聞こえた。
振り返ると鈴のついた杖が二本、地面に突き刺さっていた。
ここに来るまでにはまったく気づかなかった。
言い伝え通りの光景に、僕は息をのんだ。
怯えたが、ふと微かに弟の声が聞こえ、僕は口を閉じて意を決した。
二つの鈴杖の間をくぐると、周りの空気が一段と寒くなった。
もともと暗かった景色に青みがさした。
月明りとは異なる、もっと冷たくて異様な光が森の奥から届いてきていた。
泡がいくつも破裂するような音が漏れ聞こえてきた。
本能的に危険だと思ったが、その濁音の中に弟の笑い声が聞こえたため、僕は息を止めたまま急いで森の中へと分け入った。
頭の中は弟を取り戻すことでいっぱいだった。
森の奥にあった光景は、今でも脳裏に焼き付いている。
青い炎としか言いようがないものが地面から噴き出ていて、それを取り囲むように、奇妙な黒い人々が立っていた。
手も足も普通の人より二倍はあった。
それでいて、頭は人間と変わらない大きさだった。
顔はなかった。鼻や目があるはずの場所にはアジサイのような花弁がついていた。
アズナ村の住人の異形の姿に、僕の全身が痺れた。
弟は、炎の前にいた。
いなくなった弟の友人もそこにいて、抱き合って笑っていた。
その腕も足もすでに僕より長くなっていた。
二人とも笑っているが、声だとわかるのは弟のものだけだ。
友人の顔はすでにアジサイになり、泡の割れる音しかしていなかった。
弟は鼻先から血を流していた。
鼻がめくれ、目がつぶれ、口が裏返り、皮膚の裏側がアジサイのように襞を作り始めていた。
僕は声にならない叫びを上げて森を駆け戻り、二本の杖の間を潜り抜けた。
景色に月の明かりが戻り、滝つぼに向けて胃の中のものをすべて吐いた。
振り返ると杖はもうなくなっていて、青い光も弟の声も届いていなかった。
それからどうやって家に帰ったのか、僕は憶えていない。
ふと気づくと弟はいないことになっていた。
死んだとか行方不明とかじゃない。
最初からいなかったことになっていた。
弟の話を両親に振ると、二人とも本当にわからないという顔をした。
僕の知り合いも同じ反応をした。
僕は自分こそおかしくなったんじゃないかと思い始めるようになった。
あの田舎町は市町村合併ですでに名前を変えている。
僕は就職を期に田舎町を離れ、両親も離婚して今はお互いに別の町で暮らしている。
弟のことを話す機会も、アズナ村の言い伝えをする相手もいない。
ただ今は、匿名で何でも発信できる時代だ。
こうしてインターネットに放流しておけば、あの村のことを知っている人が思い出すかもしれない。
アズナ村のことを、そして弟のことを。
今やすっかり年寄りの仲間入りをしてしまった僕が弟にしてやれることといえばこれくらいしか思いつかない。
- 工事中
- 工事中
- 工事中