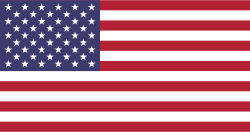公開している記事の「無断引用」、「無断転載」は禁止しております。
ここで公開している話はすべてオリジナル小説で登場する人物、場所は架空でありフィクションです。
体調が悪い時は逆に健康に悪化させる可能性があるため読むのを中止にしてください。
雨の降りしきる夜、私は終電を逃してしまった。
岡山県の山深い地域を走る閑散としたローカル線。
次の始発は朝の5時だという。
駅員は既に帰ってしまい、待合室で一晩を過ごすしかないと諦めかけた時だった。
「まだ一本あるよ」
背後から声がした。
振り返ると、古びた駅員帽を被った老人が立っていた。
白髪交じりの髭を蓄え、深いしわの刻まれた顔には、どこか悲しげな表情が浮かんでいた。
「霧待線の終電がもうすぐ来る。乗れば街まで出られるよ」
地図にない路線名だったが、この寒さの中で待つよりはましだと思った。
老人の言葉に従い、ホームの端にある階段を下りると、確かにそこには別のホームがあった。
階段を降りるにつれ、周囲の空気が変わっていくのを感じた。
湿った冷気が肌を刺し、何か得体の知れない匂いが鼻をついた。
霧が立ち込める中、古びた木造の駅舎が見えてきた。
「霧待駅」と書かれた看板が風に揺れている。
不思議なことに、さっきまで降っていた雨は止んでいた。
代わりに、濃い霧が辺りを包み込み、視界を遮っていた。
間もなく、古い客車を引く蒸気機関車が滑り込んできた。
黒い車体に赤錆が浮き、車輪からは不気味な軋み音が響く。
乗客は私一人。
車内は昭和初期のままの内装で、木の匂いと古い革の香りが混ざっていた。
座席の布地は所々破れ、天井には蜘蛛の巣が張っていた。
列車は動き出し、窓の外は深い霧に包まれていた。
時折、霧の向こうに人影が見えるような気がした。
目を凝らすと、それは人の形をしているようで、しかし何か違和感があった。
腕や足の長さが普通ではなく、頭部の形も奇妙だった。私は思わず目を逸らした。
携帯電話を取り出したが、圏外表示のままだった。
時計を見ると、針が狂ったように逆回転している。
不安が胸をよぎる。
この列車は本当に街へ向かっているのだろうか。
車内アナウンスが鳴り響いた。
「お客様にお知らせいたします。
この列車は霧の世界を巡る特別列車です。
次の駅では、あなたの過去が待っています」
何かの冗談だろうか。
しかし、アナウンスの声には妙な説得力があった。
一時間ほど経っただろうか。
列車はゆっくりと停車した。
「次は影待駅、影待駅です」とアナウンスが流れた。
さっきは確かに「霧待駅」だったはずなのに。
ホームに降りると、そこは廃墟のような駅だった。
薄暗い照明の下、待合室のベンチに腰掛けた老婆が一人、編み物をしている。
彼女に声をかけようと近づくと、老婆はゆっくりと顔を上げた。
顔がなかった。
恐怖で足がすくみ、すぐさま列車に戻ろうとしたが、列車は既に発車していた。
駅の外に出ると、そこは見知らぬ村だった。
街灯もなく、月明かりだけが道を照らしている。
家々は朽ち果て、瓦が落ち、障子が破れていた。
まるで何十年も前に廃村になったかのようだ。
遠くに灯りが見えた。
誰かに助けを求めようと、その家に向かって歩き始めた。
しかし、どれだけ歩いても灯りは近づかない。
むしろ遠ざかっているようだった。
足元を見ると、道は血の色に染まっていた。
後ろから足音が聞こえた。
振り返ると、三人の村人が立っていた。
血で汚れた作業着を着て、手には鎌や斧を持っている。
彼らの目は赤く光り、口元には獰猛な笑みが浮かんでいた。
「お客さんが来たぞ」一人が言った。
「今夜の生贄だ」もう一人が答えた。
「逃がすな」最後の一人が叫んだ。
彼らは一斉に私に向かって走り出した。
私も必死で逃げた。
道なき道を走り、藪をかき分け、崖を転がり落ちながら逃げた。
背後からは村人たちの叫び声と、斧や鎌が空を切る音が聞こえてくる。
息も絶え絶えに走り続けると、突如として霧が晴れた。
気がつくと、また駅に戻っていた。
しかし今度は「待霧駅」という名前になっていた。
ホームには先ほどの列車が止まっていた。
逃げるように列車に飛び乗った。
車内には先ほどいなかった乗客が数人いた。
彼らは皆、虚ろな目で前を見つめている。
話しかけても反応はない。
よく見ると、全員の首筋に同じ模様の痣があった。
その痣は、まるで小さな顔のようにうごめいているように見えた。
列車は再び動き出した。
窓の外を見ると、霧の中に無数の顔が浮かんでいる。
彼らは皆、苦しそうな表情で列車を見つめていた。
その中に、自分の顔があることに気づいて背筋が凍った。
「次は終点、無待駅です。無待駅です」
アナウンスが流れた瞬間、車内の照明が消え、乗客たちが一斉に私の方を向いた。
彼らの目は赤く光り、口が裂けるように広がっていく。
その口からは長い舌が伸び、私に絡みつこうとしていた。
恐怖のあまり、私は非常ドアを開け、走行中の列車から飛び降りた。
闇の中へ落ちていく感覚。
そして、強い衝撃と共に意識が遠のいていった。
目を覚ますと、私は最初の駅の待合室にいた。
朝日が差し込み、駅員が私を起こしていた。
「お客さん、ここで寝ると風邪ひきますよ」
夢だったのか。安堵のため息をついた私は、駅員に尋ねた。
「この辺りに霧待線という路線はありますか?」
駅員は顔色を変えた。
「50年前に廃線になった路線です。事故があって…」
駅員の話によれば、霧待線の終電が崖下に転落し、乗客全員が亡くなったという。
事故があった日は、今日と同じ日付だった。
安堵したのも束の間、ポケットから何かが落ちた。
拾い上げると、それは古びた切符だった。
行き先には「霧待駅→影待駅→待霧駅→無待駅→現世外」と印字されていた。
そして切符の裏には、鉛筆で走り書きされた文字があった。
「また来てね」
駅を出ようとした時、改札口で切符を出そうとしたが見つからない。
駅員に事情を説明すると、彼は不思議そうな顔をした。
「この駅に改札はありませんよ。無人駅ですから」
振り返ると、確かにそこに改札はなかった。
しかし、私の目の前には確かに駅員がいる。
彼は笑顔で言った。
「お客さん、次の列車はもうすぐです。霧待線の始発ですよ」
彼の首筋には、あの痣があった。
窓の外を見ると、駅は徐々に霧に包まれ始めていた。
そして遠くから、蒸気機関車の汽笛が聞こえてきた。
霧の中から、あの列車が姿を現す。
そして、私の足は勝手に動き出し、その列車へと向かっていった。
これが終わりなのか、それとも新たな始まりなのか。
霧の中へ消えていく私には、もうわからなかった。
- 工事中
- 工事中
- 工事中