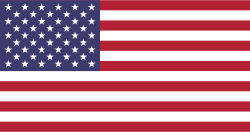公開している記事の「無断引用」、「無断転載」は禁止しております。
ここで公開している話はすべてオリジナル小説で登場する人物、場所は架空でありフィクションです。
体調が悪い時は逆に健康に悪化させる可能性があるため読むのを中止にしてください。
家を出たのは、真夜中だった。
玄関の音を立てないようにリュックを担いで、灯(あかり)は静かに階段を降りた。
母親はもう自分を見ようともしない。
再婚相手とは目も合わない。
この家に居場所なんて最初からなかった。
だからもういい、消えてしまおうと、夜行列車に乗った。
終点までの切符を買ったはずだった。けれど、なぜかアナウンスが言う。
――つぎは、こくら。こくら、こくら。
そんな駅、聞いたことがない。
車内には他に一人、制服姿の少年がいたが、彼も不思議そうに窓の外を見ている。
外は真っ暗で、ホームの光も、建物もない。ただ、音だけがない。
列車が止まった。灯は吸い寄せられるようにドアをくぐる。
目の前にあったのは、錆びた駅名板。
《虚倉駅》と、確かに読めた。でも、それだけだった。駅員もいない。改札もない。
あるのは、鏡張りの壁と、どこまでも続くプラットホーム、そして、足音が響かない床。
「ここ、どこ……?」
呟いても、返ってくるのは、自分の声だけ。
背後で、あの少年が言った。
「ここ、たまに来るんだ。名前が消えると、来れるみたい」
「……何、それ?」
少年には、顔がなかった。
髪と服は普通なのに、顔だけが曇ったガラスのようになっていた。
けれど、声は脳内に直接響くように聞こえる。
「君、まだ匂いがあるね。記憶の匂い。……僕はもう、ないけど」
灯は一歩後ずさった。吐く息が白くないことに気づく。寒いのに、体温の感覚がなかった。
ホームの隅では、錆びた時計が止まっていた。何年前かもわからない時刻で。
「帰りたい」
「帰れたら、とっくに誰もいないよ」
そのとき、ホームの向こうから、もう一人の人影が現れた。
長いコートにスニーカー。
学生っぽくはない。
彼女――雨音と名乗った女性は、どこか落ち着いて見えた。
「あなた、初めての人?大丈夫よ、少しすれば列車が来るわ。ちゃんと、戻れる列車が」
そう言って微笑んだが、その笑顔はどこか不自然だった。目だけが笑っていなかった。
「……あの、なんでここにいるんですか?」
雨音はしばらく黙って、構内の鏡壁を見つめていた。
「十年前に、気がついたらいたの。出ようとしても、ね。誰かが替わりに来ないと、戻れないの」
灯の心臓が跳ねた。
「それって……誰かが、代わりに囚われるってこと?」
雨音はうなずいた。
「私は、もう長すぎたの。あなたなら、きっと帰れる」
少年は首を振った。
「やめたほうがいい。あの人は、自分を救うためなら誰でも差し出す」
灯は混乱した。
誰の言葉を信じるべきか分からない。
ふと、鏡張りの壁に自分が映った。いや、映っていなかった。
さっきまであったはずの『自分の輪郭』が、少しずつ薄れている。
「……なんで」
駅が、ゆっくりと『自分を忘れさせよう』としているようだった。
名前が、記憶が、体温が、すこしずつ剥がれていく。
そのとき、アナウンスが流れた。
――列車が、まいります。まいります。……
音が逆再生されていた。
耳に触れるそれだけで、思考がざらついていく。
気持ちが悪い。胃の奥がねじれる。
その音の中に、自分の名前が混じっていた気がした。
「行きなさい」雨音が言った。「今なら、帰れるわ」
ホームに列車が滑り込む。
けれど車内には、灯の写真が貼られていた。
『行方不明:滝川灯さんを探しています』と、誰かが呼びかけていた。
「……探してる?」
胸の奥が、不意にざわついた。
どうしてだろう。顔も名前も知らないはずなのに、この少年のことを、何かに刻んでおきたくなった。
このまま、ここで起きたことすべてが夢だったみたいに消えてしまうのが、たまらなく怖かった。
手が勝手にポケットからスマホを取り出していた。
「……ねえ、これ……君の顔、撮ってもいい?」
少年は少しだけ首をかしげ、無言でうなずいた。
画面には、ぼんやりとした自分の姿と、『顔のない』
彼の影が並んで映っていた。
シャッターを押すと、ひどく微かな音がして、その瞬間だけ『何か』が確かにそこにあったように思えた。
少年が、静かに手を伸ばす。
「忘れられてなかったなら、まだ帰れる。君は、誰かの中にいる」
灯は列車に足をかけた。振り返ると、雨音が初めてほんとうに笑っていた。
そのまま、ホームが闇に溶けた。
気づいたとき、灯はベンチに座っていた。
周囲には人がいて、明るいホームだった。
駅の名前は見覚えがあった。切符も、カバンも、すべて元通りだった。
ただ一つ、携帯に入っていた『顔のない少年』との自撮り写真だけが、虚倉駅の証拠だった。
写真の背景には、あの鏡張りの壁がぼんやりと写っていた。
その場所は、どの地図にも載っていない。電車の路線図にもない。
けれど、あれは夢じゃない。確かに、あった。
それは、どこにも投稿できない記憶だった。
その夜、灯は一睡もできなかった。
駅から出てすぐ、交番で保護された。名前を名乗ると、すぐに照会がかかり、母親の泣き声が電話越しに聞こえた。
あの人が泣くなんて――灯は、どこか夢の続きを見ているようだった。
家に戻ったとき、部屋の隅に自分の写真が置かれているのを見つけた。
『おかえり』というメモが添えられていた。
それから灯は、ときどき鏡に映る自分が『少し遅れて動く』瞬間を感じることがある。
まるで、まだ駅のどこかに、自分の『欠片』が置き去りにされているかのように。
虚倉駅はきっと、今もどこかで誰かを待っている。
名前が消えかけた人を。
ある日、彼女は図書館で偶然一冊の古い時刻表を見つけた。
黄ばんだそのページの端に、確かに『虚倉』の文字があった。
小さく、手書きのような赤字で――『記憶に囚われし者、此処に眠る』と記されていた。
灯はページをそっと閉じ、図書館をあとにした。
もう、あの駅に戻るつもりはない。
けれど、忘れたくもなかった。
顔のない少年のことも、雨音のあの最後の微笑みも。
それは、消えかけた灯の心に、確かに刻まれた痕跡だった。
- 工事中
- 工事中
- 工事中