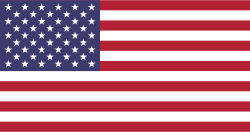公開している記事の「無断引用」、「無断転載」は禁止しております。
ここで公開している話はすべてオリジナル小説で登場する人物、場所は架空でありフィクションです。
体調が悪い時は逆に健康に悪化させる可能性があるため読むのを中止にしてください。
大学時代の友人、山本から久しぶりに連絡があった。
彼は民俗学を研究しており、日本各地の伝承を調査していた。
今回、山奥にある"朽津村"という廃村を訪れるので、一緒に来ないかという誘いだった。
「変な言い伝えが残ってる村らしいんだよ。記録がほとんどないし、面白そうだろ?」
山本のこういう話に巻き込まれるのは昔からだった。
俺は苦笑しながらも、久しぶりに会うのも悪くないと思い、同行することにした。
車で数時間、山道を進み、目的地に到着した。
村の入り口には朽ちかけた鳥居があり、その先には古びた家屋が並んでいる。
だが、その景色がどこか不気味で、時が止まったかのようだった。
陽が落ちかけた村は、どこか懐かしく、そして寂しげな空気をまとっていた。
「…静かだな」
「なあ、こういう村って、誰もいないのに“誰かがいる感じ”するよな」
山本の言葉に、俺はなんとなく頷いた。
まるで人の気配が漂っているような感覚がした。肌にぴったりと張り付くような不安感が背筋を走る。
自然の音は聞こえず、ただ風が木々を揺らす音が、遠くで微かに響いているだけだった。
村の奥に進むと、目を奪われるような大きな建物が現れた。
それは社のようだったが、鳥居が倒れ、屋根は崩れかけている。
あまりにも長い間放置されていたことが、一目でわかる。
木々が周りに生い茂り、誰も手を付けていないことを物語っていた。
それでも、不思議なことに、倒れた鳥居の前だけは綺麗に掃き清められていた。
「誰かが手入れしてるのか?」
「…いや、そんなはずないだろ」
だが、確かにそこには“何か”が息づいているような気配を感じた。
俺の体の中で冷や汗がじわりとにじみ出る。
「行ってみようぜ」
山本が先導し、俺たちは社へと足を踏み入れた。
そこには古びた畳が敷かれ、埃っぽい空気が充満していた。
日光が漏れた隙間から差し込む光が、灰色に色づいた空気を照らし出している。
祭壇の中央には、人の形をした木彫りの像が座っていた。
その木彫りの像は、微妙に人間に似ているが、どこか異質で不気味なものを感じさせる。
「……この像、どこかで見た気がする」
山本がつぶやいた瞬間、背後から冷たい風が吹いた。耳に届いたのは、低くかすれた声だった。
「ま…だ…たり…ない…」
その声は、耳の奥に直接響き、まるでその場でささやかれているかのようだった。恐怖が一気に押し寄せた。
「な、なんだ?」
ギーッという音に驚いて振り向くと、社の扉がゆっくりと閉まりかけていた。
山本が慌てて駆け寄るが、扉はピクリとも動かない。
「出られねぇ…!」
山本が焦って扉を叩くが、その音は虚しく響き渡るだけだった。
そのとき、背後の木像が、わずかに首を傾けた。
俺は息を飲んだ。確かに、“動いた”のだ。
その動きが、まるで生きているかのように感じられ、俺の心臓が激しく鼓動し始めた。
「おい、やばい…!」
「こっち!」
息を呑む暇もなく、俺は必死で脇の壁を蹴破った。
すると、古びた木材が崩れ、外に飛び出す隙間ができた。山本と俺はそ
こから転がるように外へ出た。
外へ出ると、村の様子が変わっていた。
朽ち果てて、廃屋だったはずの家々の窓に、黒い穴のような顔が並んでいた。
無数の”何か”が、まるで俺たちを招いているように見つめていた。
「走れ!」
山本の声に、俺は無我夢中で駆けた。振り向くことができなかった。
背後では、確かに誰かの足音が追いかけてきている。
足音が、どんどん近づいてくる。もう、振り返る余裕すらなかった。
ようやく入り口の鳥居までたどり着いた瞬間、俺の足を冷たい何かが掴んだ。
「まだ…たりない…」
震える声が足元から響く。
「うわっ…!」
山本が俺の腕を引っ張り、俺は地面を蹴った。次の瞬間、目の前が真っ白になりー。
—気がつくと、俺たちは車の前に倒れ込んでいた。
周囲を見回すと、村はもうどこにもなかった。
まるで最初から存在しなかったかのように、ただ静寂が広がっている。
「山本?」
息を整えながら隣を見ると、山本の姿はなかった。驚きと不安が胸を締め付ける。
「……さっきまで、確かにいたよな?」
呟いた声は、静まり返った森の中に吸い込まれ、返事は何もない。恐怖が全身を支配し、冷たい汗が背中を伝った。
急いで携帯を取り出し、山本に電話をかける。
しかし、何度かけても呼び出し音がするだけで、応答はなかった。
さらに不安が募る中、共通の知人に連絡を取るが、誰も山本のことを知らなかった。
俺はしばらく車の前で呆然と立ち尽くしていたが、やがて意を決して車に乗り込んだ。
エンジンをかけ、なんとか山道を引き返した。
家に戻っても落ち着かず、一晩中考え続けた。
翌朝、どうしても気になり、俺はついに彼の家を訪ねることにした。
インターホンを押すと、年配の女性が出てきた。
「すみません、山本佑さんはいらっしゃいますか?」
女性は怪訝そうな顔をした後、首をかしげる。
「山本?…うちにはそんな人はいませんよ。」
俺は冗談だろうと思って笑おうとしたが、その笑みはこわばり、背筋が凍るのを感じた。
—夢だったのか?
それとも、村が“足りないもの”を埋め合わせたのだろうか。
ふと、俺の足元に目をやると、黒く痩せた手形がしっかりと残っていた。
指先が震える。何度拭っても、消えそうにない黒い跡。
足元の黒い手形を見つめると、まるで“何か”が、そこにいると訴えかけてくるようだった。
「…なんで、俺だけなんだよ」
震える声は、晴れ渡った空の下で、風の音とともに消え去った。
- 工事中
- 工事中
- 工事中