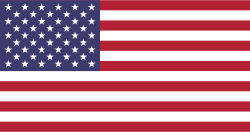公開している記事の「無断引用」、「無断転載」は禁止しております。
ここで公開している話はすべてオリジナル小説で登場する人物、場所は架空でありフィクションです。
体調が悪い時は逆に健康に悪化させる可能性があるため読むのを中止にしてください。
一章:見つけてはいけない村
長野県・奥蓼科(おくたてしな)の山中に、「爪剥(つまはぎ)」と呼ばれる集落がある。
いや、あったと言うべきか。行政記録には残されておらず、地元の古老が口を噤むその村は、登山道から外れた斜面を抜けた先に、ぽっかりと空いたように存在する。
「絶対、入っちゃいけない村があるって話、聞いたことある?」
そう言って話を持ち出したのは、大学の友人・榊だった。
同行したのは、民俗学を専攻する俺(村瀬真)、霊感があると豪語する明日香、冷静だが好奇心旺盛な映像研の槙。
調査も兼ねて訪れた俺たちは、興味本位で「爪剥集落」の噂を辿り、その入り口に立っていた。
——入った瞬間、風が止んだ。
どこか遠くで、カラカラと乾いた音が響いている。
振り向けば、来た道は霧に覆われて消えていた。
「……誰か、見てない?」
明日香が呟く。]
確かに、古い茅葺きの家屋の陰から、何かが覗いていた。
だが姿は見えない。
ただ、感じるのだ。
「視られている」という圧迫のような感覚。
村は、静かだった。
鳥も虫も鳴かず、生活の痕跡だけが異様に新しい。
炊事場の釜には煤がついておらず、洗濯物のような布が干されていた。
槙がシャッターを切った瞬間、何かが“カタリ”と落ちた。
見れば、それは人間の「爪」だった。血の気の失せた俺たちは言葉を失う。
「……出よう」
そう思ったとき、榊が言った。「あれ……俺、なんかおかしい。手が……」
彼の右手の小指の先が、わずかに透けていた。
触れても感覚がない。
俺たちは恐怖に突き動かされるように出口を探し、村の外れにある神社のような場所へとたどり着いた。
そこには、巨大な「数え棒」のような木柱があった。
一本一本に名前が刻まれている。
中には「榊亮介」という文字も。榊が震える。
——名を刻まれた者は、“ひとつずつ奪われる”。
影、声、指、顔、記憶、言葉、そして存在。
そう記された木札を見た瞬間、榊の指が落ちた。爪ではない、「指」がぽろりと消えたのだ。
明日香が叫ぶ。「ねぇ……私、自分の名前……何だっけ?」
彼女は、すでに「名前」を奪われ始めていた。
二章:奪われる順番
俺と槙は、名を刻む木柱から名前を削り取ろうとした。
ナイフで彫られた文字を削る。
だが、それは“削るたびに深くなる”奇妙な彫り方だった。
削れば削るほど、名が彫り直されていく。
まるで、刻んだ者の意志など関係ないとでも言わんばかりに。
そのとき、村の家々から「それら」は現れた。
手足のない男。
顔のない女。
名札だけが胸にぶら下がった子ども。
彼らは全て、「何かを奪われた人々」だった。無数の喪失の集合体。
「一緒に、なろうよ」
誰かがそう言った気がして、榊がふらりと足を踏み出す。
その瞬間、彼は音もなく崩れ、灰のように消えた。
存在ごと、何もかも。
そこには“いた痕跡”さえ残らなかった。
「戻らなきゃ……!」
俺は叫び、明日香の手を引いた。
だが、彼女の姿はもうなかった。
そこにいたのは、顔のない女。否、それはもう「明日香」ではなかったのだ。
俺と槙だけが、必死に元来た道を探した。
霧の中を彷徨い、記憶も曖昧になる中、槙が突然倒れ込んだ。
「……俺、自分の声が……聞こえない」
彼はすでに「声」を失っていた。
次は存在そのものだろう。
俺は彼を背負い、崩れる足場を這うように進み、気づけば崖の上に立っていた。
眼下には、爪剥の集落がぼんやりと霞んでいる。
崖から風が吹き上がる——久しぶりの風だった。
「……すまん」
俺は、槙を背負ったまま崖を飛んだ。
——目覚めたとき、病院のベッドだった。
崖の下で倒れていた俺を、登山者が偶然発見したという。
だが、俺は言葉を発せず、記憶も曖昧だった。
ただひとつ覚えていたのは、「爪剥」という名と、そこで見た“何か”の気配。
今も夢で、名前を呼ばれる。
「村瀬真」と。呼ばれるたびに、少しずつ自分が削れていくような感覚がある。
そして、ある朝。
机の上に置かれた小さな木札に、彫られていた。
——「次は、お前だ」
三章:名前が消える日
俺は今、自分が誰なのかを毎朝確かめるようになった。
名を、鏡に向かって唱える。
声がまだ出るか、影がまだついてくるか、指が十本あるか、記憶は失われていないか——毎日それを点検する。
だが確実に、何かが減っている実感がある。
自分の内側から、見えない誰かが“削って”いるような感触。
先日、大学の研究室に戻ったが、俺の机だけが存在しなかった。
教授は「君、誰だっけ?」と真顔で尋ねた。
手帳の中にも、俺の名前は見当たらなかった。
存在の輪郭が、薄れていく。
その夜、風呂上がりに鏡を見ると、背後に「榊」の姿が映っていた。
目も口もない、ただの黒い影だった。
振り返っても誰もいない。
だが鏡の中だけで、榊は俺の肩に手を置いている。
俺は今、こうして文章を残している。
もし、これを読む者がいたなら、決して「爪剥村」を探してはならない。
名を刻まれた者は、必ず“何か”を奪われる。
そして最後に残るのは——お前の名前だ。
それが奪われたとき、お前はもう「お前」ではいられない。
俺は今日も、指を数えている。
薬指の先に、感覚がなかった。
目を凝らすと、皮膚の内側から“名前”が浮かび上がっている気がする。
俺の名前じゃない。
「槙」……それとも「明日香」か。
誰の記憶を引き受けて生きているのか、もはや自分でも判然としない。
夢の中では毎晩、あの柱の前に立っている。
誰かの名が、新しく彫られていくのを見ている。
それは知っている名前だ。
SNSで見かけた人、街角で目が合った人、すれ違っただけの誰か——俺の記憶にかすかに触れた者たち。
つまり、「見たら終わり」なのだ。
俺が思い出せば、そこに刻まれる。
名を刻まれた者は奪われる。
それが、あの村の“仕組み”だったのかもしれない。
だからお願いだ。もし俺の名前を読んだなら、すぐに忘れてほしい。
村瀬真。
忘れてくれ。頼む。
- 工事中
- 工事中
- 工事中